 私が木吉くんを好きになったのは、中三の梅雨のことでした。あの日の朝は、見事な五月晴れを呈していたのに、夜には一転の雨模様。委員会で遅くなったその日、傘を忘れた彼と昇降口で偶然会ったのが事の始まり。 『いや〜は女神だな〜』 なんともリアクションに困る台詞を吐きながら、私たちは雨脚の強まっていく都内を二人で歩いた。私の鞄に忍ばせていた折りたたみ傘は、彼が持っているから、あれは俗にいう、いや言わなくても、相合傘状態。それだけで心臓が高鳴って止まらない。 隣を見上げると、『ん?』なんて視線に気付く木吉くんは、こちらの追い詰められ感なんて露知らずの顔しているから、何だか少し理不尽だ。 まさか、木吉くんがこんなに近くに来る日が来るとは思ってもよらなかった。何だかすごく日本語がおかしいけれど、あの日の私は本当にドキドキしていた。 そんな中、身長差から降り注ぐ雨が、私の眼鏡に降りかかった。 視界が不明瞭なのがもどかしくて、何気なく外しただけなのに、『へえ』と木吉くんが言うから、『ど、どしたの?』と問いかけたら、彼はまた言うのだ。 『うん。眼鏡もいいけど、ないのも可愛いぞ』 『俺はないのも好きだな』 その言葉で私は木吉鉄平に一気に落ちた。雷に撃たれたかのようだった。 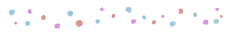  今でも時折紙面で見る、高校デビューの文字。かくいう私もその一人だ。 彼のその一言にほだされて、中学時代までの眼鏡とさよならした。高校になって初めて付けたコンタクトは正直違和感だらけだった。何人かこの変化に気付いてくれたけれど、この変化をもたらした張本人である木吉くんとは、同じ誠凛に通えどもあの日から接点すらなかった。 背中を追うだけの恋を続けて、丁度三年が経つ。あの日へ帰るように今日も雨が降っていた。 今日という日は、別に委員会が遅くなったわけでもなければ、傘を忘れたわけでもなかった。ただ、今朝方、傘立てに確かに立てたはずの雨具が忽然と姿を消していただけだ。 「あれ…?」 幾ら目を凝らして探せども、自分のそれは見当たらない。シンプルな無地の紺色だから、間違えて持っていかれてもおかしくはないし、ビニール傘と同じく持ち去っても当事者の罪悪感は少ないかもしれない。 嘘でしょ、と嘆けども、雨脚は弱まる気配は見せないし、近場のコンビニまでは走っても五分は掛かるだろう。仕方ない、親に迎えに来てもらうか、と携帯を取り出せば、液晶にまず映ったラインの通知は母からで『今日遅くなっちゃったー』なんて随分と気軽な重大な内容だった。「まじか…」と独りごとを吐いたあと、コンビニまで走るしかないようだ、と頭では分かるのに、ふと見上げた空の降雨量を見ると、昇降口の下から一歩を踏み出す勇気が出せない。 「?」 ふと私の名前を呼ぶ声が聞こえる。 振り向いたなら木吉くんと日向くんと、相田さんがいる。ああ、これは男バスメンバーか。部活帰りだろうか。 「あ、え、っと…お疲れ様です」 「どうした?傘ないのか?」 「うん、まあ、あったんだけど、無くなっちゃったっていうか…」 「そーか」 「あ、でも、家まで近いし、大丈夫だからっ気にしな――」 気にしないで、と言いたかったのに、そーかそーかと相槌を打っていた私の喋りを遮って木吉くんが 「そーか、なら俺、送って帰るから」 と二人に告げる。 ええええええええ!!と慌てふためいたのは私の心中だけだったようで、言われた二人のうち相田さんは「そーお?」なんて言っている。「いい、いい、いい!ほんとっ大丈夫だから!!」という私の言葉は、木吉くんにすらまるで無視され、日向くんなんて、「フーン」となんて何と淡泊なことか。視線は二人とバッチリ合っていたから、きっと私の無言の訴えには気付いてくれただろうに、「じゃーな」「じゃーねえー」とさっさと雨の中に身を投じた。何だか若干、裏切られた気分。 「それじゃあ、帰ろう」 そんな優しい顔で笑いかけられたら、どうしていいか良く分からないよ…。あれよあれよという間に、木吉くんとの距離が縮まってきて、彼は自分の傘のパンと開いて、「ほい」とそのまま私をその中へ入れた。 断りの言葉は出てきそうで出てこなくて、う、とか、あ、とか随分と言葉を詰まらせたあと、 「よ、よろしく、お願いします…」 そう言うしかなかった。 情けない声は、殆ど雨音に消えそうだったのに、木吉くんは受け取ったように笑った。 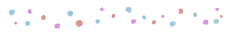  雨脚の強まっていく都内を二人で歩いていく。 「部活はどう」とか「もうすぐ期末試験だね」とか「志望校決まった?」とか、私はずっと彼に語りかけた。まるで自分じゃないくらいによく喋る私の心は、鬱陶しくないかな、とか、話つまらなくないかな、とか不安でいっぱいだった。喋れば喋るほど不安になるのに、それを止めて沈黙になることも怖かった。悪循環は私を混乱させていく。ただ、時折伺う木吉くんの顔がいつものように穏やかなのだけが救いだった。 肩を並べた、この距離がドキドキする。はにかむ表情を見上げて見るこの位置が新鮮で、鳴っている心臓の音が体に痛い。つい口を噤んだ時に、 「ん?どうした?」 「あ、っ…ううん、なんでも…」 ふとした訪れた沈黙に敏感に気付く木吉くんは、こちら側の裏の気持ちまで気付いているんじゃないかと心配になって必至に誤魔化すしかなかった。恋焦がれた乙女の焦燥を、視線一つで察知する彼は、なんだかとっても理不尽だ。 「いや〜懐かしいな」 「え?何、が…」 「ほら、昔もこうやって帰ったろ」 その言葉一つに、鼓動はまた飛び上がる。中三の梅雨の日が頭を駆け抜けて、眩暈のように頭がくらくらしてくる。「お礼、ずっとしたかったんだ」と木吉くんが繋げた。どうやら、木吉くんがあの日のことを覚えていてくれたらしい。忘れていなかったらしい…。 「覚えててくれたんだ…」 混乱した頭は、思考をそのまま吐露する。はっと気付いた時に口を覆いたくなったけれど、出てしまった言葉は取り戻すことは出来なかった。ああ、またやってしまった!と心が一層慌てた時、木吉くんが 「当たり前だろ〜」 と言うものだから、咄嗟に彼の顔を伺った。 彼は、変わらない笑顔を携えたまま誰に。向けているのか分からない笑顔をひとつ見せると、また私の視線に気付いた。合った視線にびっくりして、目を逸らそうと思ったのに、私よりも先に木吉くんが目を泳がせたものだから、こちらはタイミングを失ってしまう。木吉くんは、傘を持ってないもう一方の手の人指し指で頬をかきながら、「はは」と困ったように笑った。何だかとても恥ずかしくなって、私は顔を俯かせた。 落とした視線の先で、半ば自動的に足が歩いている。三年間履いているローファーにのすぐ側を、木吉くんの大きな足がちらちらと掠めていた。 「そういえば、、あの頃は眼鏡だったよな」 「あ、うん…やっぱり、体育とか、眼鏡だと色々…」 言いながら、何ともくだらない理由しか思い浮かばないものだと痛感する。あなたに言われたから、なんて言えるはずもない。「確かになあ」と、うんうん、と頷きながら彼は言ってくれた。きっと視力のいい彼には関係のない話題だろうに、その思いやりが嬉しかった。 木吉くんは一体どう思っているんだろう。何人かにはコンタクトにしたことを指摘されて、感想を言われたけれど、最も重要なのは、木吉くんの感想だ。 アスファルトが大部分を占める視界の先、大分家が近くなってきたことを知る。あれから三年を過ごして、あの日の偶然性を思い知った。三年目に訪れた今日の日も、きっと事故みたいなものなんだと思う。恋に奥手で縮まらない距離は仕方ない。もう卒業まで木吉くんと帰る日なんて来ないだろう。残りわずかしかないなら、と。 「あ、えと、そ、その」 「ん?」 「その、眼鏡じゃ、なくな、ったけど……」 せめて、せめて、と必至に高鳴る鼓動を抑制しながら、声を震わす。 「どう、か、な……。」 恥ずかしすぎて言葉尻が弱くなって、自分ですら何を言ってるか分からない。どういう顔をしたらいいか分からなくて、下唇を噛みながら、必至に木吉くんの顔を見上げた。さっきまで抑制していた鼓動は、タガが外れたみたいにばくばくと鳴った。ああ、何だか今泣きそうだ。 木吉くんは一度、意外そうな顔を見せたあと、またいつものように笑った。 「うん、やっぱり、可愛いと思う」 「あ、っ…あり、がとう…っ」 普通に笑えばいいだろうに、上手く笑えなくて、きっとぎこちない笑みを返したことだろう。もう家は目の前だ。逃げ帰るように「あ、」と言いいながら手を動かせば、私の仕草に誘われて、彼も『』の名のついた表札を目に留めた。せめて別れの挨拶くらいは上手に言って別れようと思っていたら、 「惚れてよかった」 と木吉くんがぽつりと言う。 何を言ったのかが理解出来なくて、数秒止まったあと、「え?」と木吉くんを見上げた。先ほどのお別れのプランなんて頭から吹っ飛んで、彼を凝視するのに、木吉くんは何食わぬ顔で表札を指差したから、それに誘導されて私はもう一度、見慣れすぎた自宅の表札を見つめる。 「家ここだよな」 「う、うん」 「じゃあ、また明日学校で」 「あ…うん、また…明日」 もしかして、聞き間違いだったのかな。そうだ、こんな都合の良いことなんてあるはずがない。きっと頭がエンドルフィンに包まれすぎて、一瞬の白昼夢を見たんだろう。そんなことを思っている間に、木吉くんは「じゃあ」と言って足早に立ち去っていった。 結局、感謝の気持ちを述べるタイミングを失ってしまった。まだ、声を上げれば届く距離にある後ろ姿を見つめながら、そうだ明日の朝言おう、そうすればまた接点になる、なんて打算を働かせながら、奥手はまた逃げた。おやすみなさい、と心で呟きながら、ああ母がいないから夕飯の支度をしなくては、と現実に頭が切り替わったその瞬間、 「ー!」 と昇降口で出会った時と同じように、私の名前を呼ぶ声が響く。 びっくりして、咄嗟に彼の歩んでいったほうへと向き直った。すると、つい先ほどまで背を向けていた彼が振り向いている。お互いの姿を見つけたあと、木吉くんは「」ともう一回私の名前を呼んだあと、俯きがちにしながらいつもの調子で笑って、すうと息を吸い込んで。 「大好きだー!」 全く状況を飲み込めなくて、私はぽつんとその場に静止する。 すると、木吉くんは朗らかに笑って、何か言ったあと駆け足で雨の路地へと消えていった。その言葉の意味が頭の中でようやく繋がった時には、顔を真っ赤にするしかなかった。 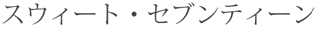 (翌朝の朝は、良く晴れた五月晴れの日でした。) --------------------------- 企画サイト『かわいくなりたい!』様へ。素敵な企画をありがとうございました。 ▽お借りした素材様 はこ(http://hacoism.ame-zaiku.com/) ふわふわ。り(http://shimizumari.com/fuwa2li/) |